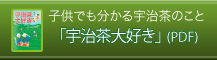ホーム > 登録基準の該当性
登録基準の該当性
世界文化遺産の評価基準6項目(6項目のうち一つ以上適合すること)
- 人間の創造的才能を表す傑作である。
- 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
- 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在である。
- 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
- あるひとつの文化を特徴づけるような伝統的居住形態若しは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である。
- 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
該当する登録基準について
上記の評価基準のうち、該当するのは以下の項目である。
| 該当する登録基準 | 内容 |
|---|---|
III【文化的伝統や文明の存在を伝承する証拠で希有な存在】現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明(の存在)を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。 |
日本の緑茶という固有の文化的伝統の起源と伝統的生産技術を伝承する証拠 「抹茶」「煎茶」「玉露」に代表される日本の緑茶は、中国では途絶したとみられる「蒸し製法」と粉末茶に湯を注いで飲む喫茶法及び茶を湯に浸してエキスを飲む喫茶法が、京都府南部の山城地域で生まれた「覆下栽培」と「宇治製法」という生産技術によって日本独自の緑茶へと進化したものである。宇治茶の文化的景観は、日本の緑茶という固有の文化的伝統の起源であり、その伝統的な生産のあり方が現在に継承されている。 |
V【ある文化を特徴づける土地利用形態の見本】あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)
|
日本の緑茶生産を特徴付ける土地利用と景観宇治茶の生産は、山城地域の自然環境条件を活かしつつ、日本独自の生産技術及び流通・消費条件によって、茶園、茶工場、茶問屋等からなる独特の土地利用と景観を形成している。その土地利用と景観は、生産に関わる技術革新と合理化により、有機的に進化を遂げつつ現在に継承されており、日本の緑茶生産に関わる土地利用と景観を代表する例である。 |
VI【人類の歴史上の顕著な普遍的意義を有する出来事や伝統、思想、信仰、芸術との関連】顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。 |
喫茶文化の形成への寄与日本固有の喫茶文化の形成にも、宇治茶は寄与してきた。「抹茶」の存在は日本の精神文化を代表する「茶の湯」の大成を促し、「煎茶」や「玉露」は「煎茶道」の隆盛をもたらすなど、社会的、文化的、思想的に強い影響力を持つ固有の喫茶文化の形成を支え続けた。また「煎茶」は18世紀以降全国に普及し、急須で茶を淹れるという日常生活に根付いた喫茶文化を一般化させることとなった。 |